
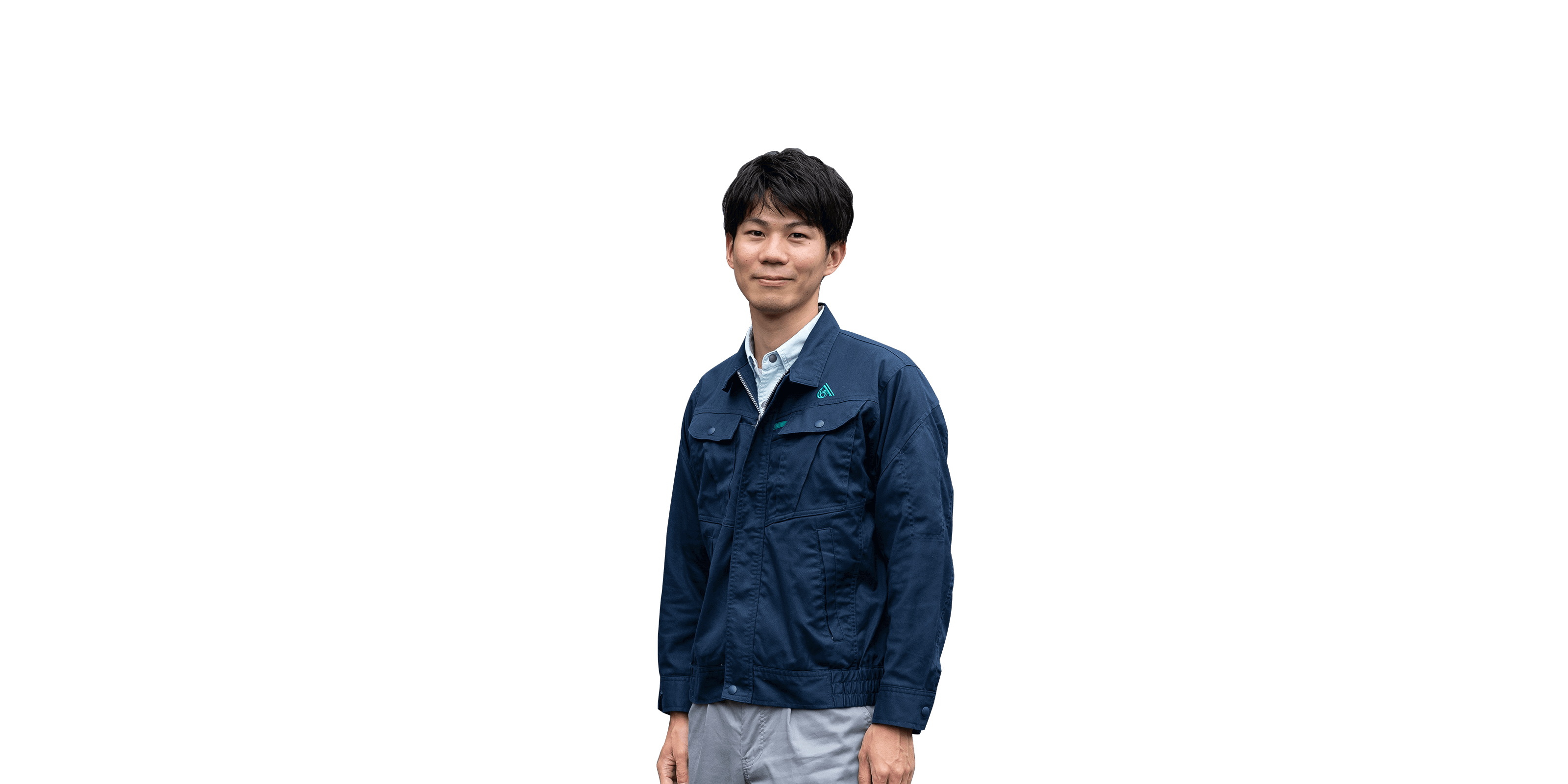
Rikuto Okuno
奥野 陸人
研究開発
2021年入社
未来科学研究科 建築学専攻 修了
※内容は取材当時のものです
技術を生み出し、
会社の強みをつくる
Episode
自ら行動し、成長につなげる


巨大な実験器具を前に、ただ立ち尽くすことしかできなかった。彼は学生時代から、建物の構造に関する実験に携わっていた。しかしながら、企業の研究開発職として行う業務は勝手が異なる。入社して数ヶ月で挑んだ初めての実験は、先輩の動きを見るだけで終わりを迎えた。
「研究開発は新たな技術や製品を生み出す仕事です。学生の頃に構造の研究をしていたとはいえ、それを生業にするには経験が足りません。だからこそ、悔しく思いました」
このもどかしさが、彼を成長させた。先輩の仕事ぶりを参考にしつつ、「こうすればもっと良くなるかも知れない」と自分なりの考えを持つように心がける。研究開発はトライ&エラーの繰り返しのため、従来の手法に固執するのではなく、常に最善の方法を探らなければならない。時には「自分はこうするべきだと思います」と、主張することもある。若輩者の発言ながらも、上司や取引先の人たちは真剣に向き合ってくれた。


次第に自分でできる仕事が増えてきたと実感する。ある協力先の研究所で実験を行う際、急遽先輩が来られなくなったため、彼が実験を取り仕切ることとなった。不安はあったが、自分がやるしかない。
「急遽の出来事で焦りもしたのですが、無事に取り仕切ることができたので大きな自信になりました。先輩に教えていただきながら、自分で考えて行動できるようになっていたので、うまくいったのだと思います」
若手の意見を受け入れ、成長を促してくれる環境がここにはある。彼が携わった技術が、当社の未来の礎となることは間違いない。


Q & A
仕事内容
私が勤務する技術研究所では、当社の保有している技術・製品をより発展させるための実験や研究、または現場の技術支援を行います。なかでも私は、当社の耐震技術・製品である「折返しブレース」の研究開発に携わっています。既存の技術をより進化させつつ、コストダウンを実現できるように実験の計画を立てて実施し、データの分析を行います。当社の技術力の高さは、ここから生まれています。
入社理由
数あるゼネコンのなかでも、当社のキャリアは幅広いのが特徴です。施工管理や設計、研究開発などさまざまな職種を経験しながらステップアップすることができます。また就職活動中に参加した会社説明会の座談会では、部門の垣根を越えて社員同士がフランクに接しており、和やかな雰囲気のなかで働くことができると感じたため、入社を決めました。
仕事の醍醐味
これまでにない技術や製品を解明したり、生み出したりするのが研究開発の役割です。そのため、うまくいかないことも多く、時間と労力を要する仕事です。しかし、同じチームの研究員や共同研究先の会社の方々と意見を交えることで、分析と考察が進み、より良いものが生み出されます。そのプロセスに面白みを感じます。まだ大きな成果は残せていないものの、自分が提案・努力した内容が、実用化・製品化されたら嬉しいです。
今後の目標
現在の研究を実用化につなげるためには、構造設計の知識と理解も必要になります。現在は構造設計の勉強をしつつ、自身のステップアップを志して一級建築士の取得にも取り組んでいます。将来的には、研究開発業務で専門知識を磨きつつ、実際の建物に対して技術提案を自ら行い、当社の建築分野全体に貢献できるようになりたいと考えています。







